G Scale Shop
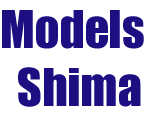
Gゲージクラブへのお誘い
鉄道模型は一人で楽しむのも良いですが、好き者が集まって遊ぶのも楽しいですよ。
みんなでわいわいがやがややりながら、知らないことを教えたり教えてもらったり。
DCCに精通しているメンバーもいますので、デコーダーの積み方・設定など一人で
悩んでもなかなか解決できないことも教えてもらえます。
東京都日野市でほぼ毎月開催していますので、ご都合が合えば参加お待ちしています。
(無料駐車場あり)
ゲージはGゲージとHO(16.5mmであれば何でも可)を交互にやっています。
細かい規定などは一切設けていませんが、唯一参加費(維持費)として1回1000円の
ご負担をいただいております。
不定期ですが”遠足”と称してみんなで遊びに行くこともあります。
ご参加をお待ちしております。
初回連絡は当店にお願いします。
